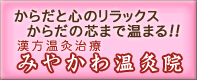■みやかわ温灸院 院長のブログ
過去の記事はこちらから→「鶯谷書院」
最後の投稿
-
読者の詳細は分からないけど、「読んでますよ」と声かけしてくれる人がいます。一方的に投げているつもりなのに、キャッチしてくれる人がいるのかと思うと、すこし照れてしまいます。
以前、書きましたように、今年限りで、温灸院・薬局を閉じることになりました。ホームページも閉鎖しますので、このブログも、これが最後です。ながい間、ご愛読ありがとうございました。
2024年 12月 28日 釜たきご飯
-
土鍋で炊いていたご飯は、土鍋の老朽化で、鉄釜で炊くことにしました。
はじめちょろちょろ、なかぱっぱ、赤子ないてもふた取るな
といわれるけど、火を止めるタイミングがわからないので、20分すぎにフタをとって、炊き上がりをみています。時間どおりだと焦げるし。
火力が安定しているガスコンロだからいいものの、薪をくべているなら、火力の調整は難しかろう。安易なものには行きやすいが、煩わしいものに戻るのはたいへん!
くるまも、ATからマニュアルに戻そうかな〜
2024年 12月 27日 滝川亀太郎旧居
-
滝川亀太郎(1865〜1946)は、『史記会注考証』の著者。ぼくが、1990年代に『史記』扁鵲倉公列伝を研究していたときに、とてもお世話になった注釈書です。
先月、島根の松江城を観光したとき、お堀の北側に武家屋敷があったので見学したら、なんと滝川亀太郎が住んでいたという家でした。偶然なのでおどろきましたが、『史記会注考証』を思い浮かべながら、屋敷を見学しました。
おもいだせば、『史記』を勉強しているとき、隣町の越谷市の文教大学図書館の町田文庫に『史記』関連の資料が豊富にあったので利用させていただきました。今から30年ほど前ですから、ぼくが40歳前後のときです。2000年を境に(師匠の病没)、扁鵲倉公列伝の研究から手を引きました。
偶然といえば、柳川市を観光していたとき、大きな地図に「下村湖人旧居」とあったので、勇んでタクシーをとばして行きました。そのころは『論語』を読んでいたので、『論語物語』の著者の名前をみて、その偶然さ驚きました。
2024年 12月 25日 子守と体幹
-
昭和初期の子守の写真です。大抵は、お姉さんが、妹や弟をおぶっています。おぶったまま、外で遊んでいたようです。
孫が3人もいて、だっこするつらさを知る身としては、小学生のお姉さんがおんぶしているのも、たいへんなんだろうね、と同情してしまいます。
したの写真なんかは、自分の背丈の3分の2くらいの妹を負ぶっています。上の写真の左はしのお姉さんは、顔の大きさが同じくらいの弟をおぶっています。
ふたりの妹、弟は、3〜4歳くらい、体重は15キロ前後と思われる。 大人でも大変なのに、小学生のお姉さんがおぶっているのですから、体幹がきたえられますね。
体幹ばきばきのお姉さんたちが、現在の80歳、90歳のおばさまに成長したのですよ。きっと。
2024年 12月 23日 ほうき
-
掃除機が出回る前は、ほうきで掃除していました。背丈ほどあるほうきは、立ちぼうきといっていましたが、イラストによれば庭ほうきというらしい。その半分の背丈は、なんというかわすれたが、イラストによれば荒神(こうじん)ほうきというらしい。ほうきA・B・Cで良いのに、ひとつひとつに名前があるのが、ほほえましい。それが、脈絡ないのが、さらにほほえましい。
小学校の家庭科では、ぞうきんをぬったの思い出しました。ストッキングを裂いて、はたきを作ったこともありました。
これらの道具は日用ではなく、ことばに死語というのがあるのにちなめば、死道具というのかも知れません。
2024年 12月 18日